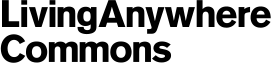住む街は1つじゃなきゃ、なんてない。
大阪とニューヨーク。個性あふれる2つの都市を行き来しながら、自身が編集長を務めるオピニオンメディア「milieu(ミリュー)」など、さまざまなメディアを通じ、独自の視点で情報発信を続ける文筆家・塩谷舞さん。過酷なニューヨークのコロナ禍を目の当たりにしながら、塩谷さんが見いだした新しい世界の生き方とは。はたまた二拠点生活を通じて手に入れた、新しい自由とは。

コロナ禍によって、半ば強制的に始まった感のある「リモートワーク」。最初は恐る恐るだったリモートワークも、ふたを開けてみれば「なんだリモートでも、結構仕事ってできるんだ」。そんな手応えに変わった人も多かったのではないだろうか。働く場所から自由になれば、住まいの選択肢はグンと広がる。以前は別荘を持つ、限られた人のものと考えられていた「二拠点生活」も、一気に現実味を帯びてくる。フリーランスのライターである塩谷舞さんは3年ほど前から、そんな二拠点生活を続けてきた一人だ。
「どこで」ではなく、
「誰が」「何を」生むか。
それが大切なんじゃないか。
アーティストとして活動を続けるパートナーのたっての希望で、29歳で海外移住を決意。3年近くに及ぶ大阪とニューヨークの二拠点生活を経て、いよいよ本格的に移住が決まった2020年。塩谷さんはニューヨークでコロナ禍に見舞われた。

「今は多少落ち着いてきた感もありますが、4月のニューヨークは救急車のサイレンが鳴りやまず、本当に悲惨な状況でした。家から出るのは週1回の買い物程度。普段は家でニュースを見ているだけだったので、ニューヨークの現状をこの目で見たという実感もなく、分かるのは半径1kmの生活圏内のことぐらい。それでも道路脇にラップでぐるぐる巻きにされたマットレスが捨てられているのを見たりすると、『もしかして亡くなった人が……』と危機感を肌で感じることも多かったです」

異国の地で経験する、初めての非常事態&ステイホーム。感染拡大状況や、それに伴う外出規制もニューヨークは日本よりはるかに厳しかった。しかしステイホームは、同時に塩谷さんに「内省」という貴重な時間も与えてくれていたと話す。
「当然といえば当然ですが、仕事で依頼される記事が『ステイホームをどう過ごすか』とか『コロナに対してどう心構えをするか』といった内容のものばかりになっちゃったんです。経済誌も、ファッション誌も、まるで世界の共通一次試験のように、どの国のどの立場の人も同じ課題に頭を悩ませているんだと感じました。普段なら旅に出たり、何か珍しいことをして、それを書けばそのまま個性になる。でも、みんなと同じ状況を過ごす中で、自分に書けることって一体何だろう?と悩んでしまいました」

「ヨーイどん、の同じ課題に私はどう答えるのか。それは自分の内側や社会のあり方を、今まで以上に慎重に見つめる機会でもありました。コロナに対してどう心構えをするか?と問われても、私自身、ニュースを見て落ち込んだり、不調が続いていたんですよね。残念ながら、私は弱者を助けられるヒーローではなかった。でも書かなきゃいけない、仕事だから(笑)。ならば……と、崩れ落ちそうな自分をひっくるめて文章を書いていくと、思いのほか受け入れてくれる方が多かったんです。そのとき、言葉を発する側が必ずしも強くなくてもいいんだ、と力が抜けました。自分の存在が、社会の中でどういう位置づけにあるのかを再認識させてもらえた瞬間でした」
ダメになってしまう自分だっていること。それを受け入れてくれる人が、一人でも多くいれば、社会はもっと生きやすくなる。これも塩谷さんが、ステイホーム中の「内省」を通じて感じたことだ。
コロナをきっかけに大都市から郊外へ
そして塩谷さんは、コロナをきっかけに「住まい」のことも見つめ直した。
「前は、ブルックリンのウィリアムズバーグという地区の高層住宅に住んでいました。街は活気があり、次々と話題のビジネスが体験できる、トレンドの集まった場所です。けれども、ステイホームになるとどこにも行けなくなり、ただただ家賃が高い部屋に。高層階の落下防止対策で窓がほんの少ししか開かない上、我々が住んでいたのはバルコニーのない部屋……。ずっと夫と二人で狭い部屋の中で在宅作業をしていると、もう本当に酸素が薄い! 水面で酸素を求めてパクパクする金魚のように、うっすら開けた窓辺に行っては酸素を吸うようになってしまいました。そんな最中に、夫婦間での価値観の違いも大きくなり、壮絶なケンカを繰り返し……。話すと長いので省略しますが(笑)、話し合いの結果、もっと広い場所が必要だとなり、酸素とお互いのスペースが十分に確保できる住まいを求めて引っ越すことに。とにかく、まずは酸素を!と(笑)」

ブルックリンの流行の地から、ファミリー層の多いニュージャージー州へ。移ることへの抵抗はなかったのだろうか。「『都落ち』とか『島流し』なんて言いますけど、そろそろ反対に『都上がり』『島上り』があってもいいんじゃない?と思っていて(笑)」。そこには、塩谷さんが経験してきた二拠点生活を通しての気づきも大きく影響している。
「子どもの頃から23歳までずっと、大阪の郊外にある実家で過ごしてきたのですが、住宅街しかないエリアなので本当に退屈で。はやく大都会に出たくて仕方がなかった。だから就職先は原宿にある会社を選んだし、その次はニューヨーク。けれども、ビザの関係で二拠点生活を余儀なくされる中で、ずっと自分の中にあった『都会こそが最高!』という絶対的な信仰心が崩れてきたんです。
実家のある大阪の千里ニュータウンと、ニューヨークを行き来していると、次第に『何もない』と思い込んでいた千里ニュータウンだって、実はずっと魅力的なんじゃない?と思えるほどになってきて。東京もニューヨークも確かにすごく魅力的だけど、だからといって地方都市がなんら劣っているわけではない。23年間住んでいるときは気づかなかったけど、離れてやっと、気がつくことができました」
そんな気づきのきっかけとなったのが、実家近くにあるギャラリーの存在だった。
「住宅街の真ん中に、とても素敵なギャラリーがあるんです。外観は完全に家なのですが、ギャラリストさんの深い愛によって営まれている。交通の便も決して良くはないのに、個展となれば日本中、世界中から大勢の人が足を運んでいる。そこで生まれる空気や、集まる人たちの静かな熱狂を見ているうちに、何もない街なんて、ひとつもないんだと考えるようになりました。どこに行っても、少なくとも自分がいる。まず自分がいれば、何かを考えられるし、好きな空間もつくれる。人だって呼べる。それだけでもう、立派な観光地じゃないかと(笑)。大都市の魅力にあやからずとも、自分の信念で暮らしていけるって魅力的なこと。だから『都落ち』ではなく、『都上がり』だと認識しています(笑)」


複数の拠点を持つ=複数の視点・思想のレイヤーを持つこと
とはいえ、いまだ「都会」はチャンスをつかみたい人にとっては格好の場所なのも事実だ。
「今月、ずっとコロナで休止していた夫・國本怜の個展をやっと開催できたのですが、場所がマンハッタンのソーホーということもあり、本当に多くの出会いに恵まれました。ふらっと入ってきた人が、超有名ギャラリーのディレクターさんだったり、ニューヨークのアートシーンを牽引(けんいん)してこられたアーティストさんだったり……。駆け出しのアーティストである夫にとっては、最高の環境でした。ソーホーという場所は、多くの人が「あのあたりに行けば何か面白いことがあるぞ」と思って歩いているから、偶然の出会いも多い。SNSとは違って趣味の異なる人とも出会えます。表現者が多い街なので、会期中に親しくなったダンサーや尺八奏者の方と、最終日前日にライブパフォーマンスを開催したりも。そうしたところは、やっぱりリアルな都市の醍醐味(だいごみ)ですよね」
 (ダンサー:Yukari Osaka / 尺八奏者:Adam Robinson)
(ダンサー:Yukari Osaka / 尺八奏者:Adam Robinson)
「そういう意味では、都市と地方にそれぞれ拠点を持つのも、理想的ですよね。都市に小さな拠点を持ちつつ、生活の基盤は地方に置くような……。私自身、世の中でリモートワークが当たり前になってから、これまで距離の関係で受けられなかった仕事がドッと入ってくるようになりました。海外移住=現地の仕事に就く、というイメージがありましたが、日本の仕事をしながら海外で暮らすこともますます可能な状況になってきましたよね。越えられないのは時差ぐらい」
時代は確かに変わりつつある。こうして一人ひとりが、それぞれの一歩を踏み出すことで新しい世界はまた少し広がり、溶け合うようにつながっていける。塩谷さんの話を聞いているとそんな未来への希望も見えてくるようだ。
「私自身、海外に拠点を構えるなんて思ってもいませんでした。海外への憧れすらなかった人間ですし、すでにアイデンティティも確立された29歳での渡米。夫婦で英語も話せない。でも、ニューヨークの荒波にもまれ、出会ったいろいろな人と意見を交わしていくうちに、自分が今までいかに狭い物差しで物事を見ていたか知ることができたし、これまでにはなかった視点や思想のレイヤーを持つことができたことで、いい意味でゆるく、おおらかになれた気もします」
「いろいろな人に『日本を捨てたんやろ』とも言われるんですけど、それも違う。こっちで勝負している外国人は多かれ少なかれ、母国をどこかに背負っているように感じます。自分たちを育んだ文化を、ニューヨークで披露して、世界を震わせたい!というエネルギーに満ちています。そんな姿に刺激を受けながら、自分は文章を書くという仕事を通じて、日本を伝え、逆にまた日本へ伝える『遣唐使』みたいな役割が果たせたらなと思っていて。今の時代、そんなに選ばれし役割でもないですけど(笑)。『遠くへ行く=縁を切る』ということではなくて、むしろ新たにつなぎにいく。そんな役割ができたらなと思っています」

そう笑顔で語る塩谷さん。最後に、二拠点生活を経験して感じた発見や醍醐味について語ってくれた。
そして移動する一番の醍醐味は、ものだけじゃなくて、慣れてきてしまった価値観を小さくリセットできること。たとえ慣れ親しんだ故郷であっても、数年ぶりに訪れればカルチャーショックもありますし、新しい世界以上に発見に満ちていることもあります。
次に日本に帰れるのはいつになるか、計画すら立てられないですが……その日が来たら、これまでで一番新鮮な気持ちで過ごすことになる気がします。そのときにどんな景色を見て、どんなことを考えるのか、今はさっぱりわからない。きっとすごく揺さぶられると思うのですが、その中でまた文章を書いていくのが楽しみです。
1988年大阪・千里生まれ。京都市立芸術大学卒業。ニューヨーク、ニュージャージーを拠点に執筆活動を行う。大学時代にアートマガジン「SHAKE ART!」を創刊。会社員を経て、2015年より独立。2017年よりオピニオンメディア「milieu(ミリュー)」を自主運営。note定期購読マガジン「視点」にてエッセイを更新中。
みんなが読んでいる記事
-
 2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記
2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。
-
 2022/09/26【寄稿】友達がほしくて「いい人」を演じていたら、心が疲れていることに気がついた|少年B
2022/09/26【寄稿】友達がほしくて「いい人」を演じていたら、心が疲れていることに気がついた|少年Bライターの少年Bさんに、かつてとらわれていた“しなきゃ”についてつづっていただきました。幼少の頃から周囲とうまく付き合うことができず「嫌われ者だった」と語る少年Bさん。ある出来事をきっかけに「人から好かれるためには“いい人”にならなきゃ」と考え、コミュニケーションのあり方を見つめ直しました。その結果、どんどん友達が増えていく一方、心は疲れていったそう。“しなきゃ”と“自分らしさ”の間で悩む方に届けたいエッセイです。
-
 2023/02/16なぜ、「仕事はつらいもの」と思い込んでしまうのか|幸福学者・前野隆司
2023/02/16なぜ、「仕事はつらいもの」と思い込んでしまうのか|幸福学者・前野隆司「幸せに働く人」は生産性が3割増、売り上げが3割増、創造性が3倍高い――。仕事や上司に嫌気がさしている人からすると夢物語にも思えるような研究結果が、国内外で明らかになっています。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の前野隆司教授は、幸福度の高い人々の共通点を導き出し、幸せな職場づくりを研究する「幸福学」の第一人者。前野さんによると、世界第3位の経済大国でありながら「世界幸福度ランキング」や「女性の働きやすさランキング」などの国際調査で散々な結果を出している日本には、“不幸体質”と呼ぶべき遺伝子や文化が染みついているといいます。人が幸せを感じるメカニズムや幸せな会社の特徴、さらに一歩踏み出すために必要なことについて伺いました。
-
 2023/04/11無理してチャレンジしなきゃ、なんてない。【後編】-好きなことが原動力。EXILEメンバー 松本利夫の多彩な表現活動 -松本利夫
2023/04/11無理してチャレンジしなきゃ、なんてない。【後編】-好きなことが原動力。EXILEメンバー 松本利夫の多彩な表現活動 -松本利夫松本利夫さんはベーチェット病を公表し、EXILEパフォーマーとして活動しながら2015年に卒業したが、現在もEXILEのメンバーとして舞台や映画などで表現活動をしている。後編では、困難に立ち向かいながらもステージに立ち続けた思いや、卒業後の新しいチャレンジ、精力的に活動し続ける原動力について取材した。
-
 2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題
2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。
「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。
その他のカテゴリ
-
LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」
-
個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。